暑さも落ち着いた先日、子どもたちと一緒に清水公園(千葉県野田市)へ行ってきました!
ずっと気になっていた「フィールドアスレチック」が目的です。
1年生にはちょっとハードかな?と思いつつも、結果は…めちゃくちゃ楽しかったです!
体力が有り余っているお子さんぜひ行ってみてください!
🚗 清水公園フィールドアスレチックへ出発!
この日は、清水公園のフィールドアスレチックを目当てに朝からおでかけ。
3連休だったので少しでも混雑を避けようと、早めに家を出発して午前9時前には現地に到着しました。
駐車場はすでに数台の車が停まっている程度でした。
一番近そうな第3駐車場に車を停めて、いよいよアスレチックエリアへ向かいます。
🏁 受付と準備
清水公園のフィールドアスレチックは予約が必要なので、事前にしっかり手続きを済ませておきました。受付に並ぶ前にしっかり名前を確認されました。予約なしの人は入場に手間取っていた様子です。団体で来ていた人たちは付き添いの大人ではなくしっかり保護者の予約が必要なようでした。
そのまま受付の列に並んで会計して(キャッシュレスOKでした)入場!

我が家は着替えなど持って行ったので荷物が多くなってしまい、折りたたみカートを持参しました。
カートはベビーカー置き場やお弁当広場にポップアップテントに横付けして置いておく、で大丈夫そうです。ただし、カラスに狙われるので食べ物を置いておくのは絶対NGです!我が家の荷物もタオル類を置いていただけでしたが、しっかり狙われてつつかれて袋から出されていました。
🎒 設備・持ち物チェック
受付を済ませたら、まずは身支度を整えます。
清水公園フィールドアスレチックには、利用者向けのロッカーと更衣室があります。
ロッカーは有料でお金が戻らないタイプなので、小銭を準備しておくとスムーズです。
(濡れた服を入れるための袋を持っていくとさらに便利!)
更衣室もあるので、水上コースでびしょ濡れになっても安心。
着替えスペースがしっかりしているのは子連れにはありがたいポイントです。
ちなみにお手洗いも芝生もとてもきれいでした。ちゃんとハンドソープも置いてあってどろどろになった手も清潔に。
👟 靴についての注意点
注意したいのが靴の種類。
アスレチック内はサンダルでは入場できません!つま先とかかとがおおわれていないとNGです。
入口で注意されている方を見かけました。
万が一サンダルで来てしまっても、入口で靴のレンタルサービスがあるようなので安心ですができれば運動靴で来園するのがベストです。
🍙 お昼や休憩も安心
園内にはお弁当を食べられるスペースがいくつもあり、木陰のテーブルやベンチも利用できます。
うちはレジャーシートを持って行ってお弁当を食べました。
また、売店もあり、軽食・アイス・飲み物なども買えるので手ぶらでも楽しめます。
お昼時になると混雑していたので時間をずらすのもいいかもしれません。
チャレンジコースからスタート!
まずはチャレンジコースからスタートしました。全40個種目があります。
名前の通り、なかなかの運動量!こどもは最初からエンジン全開で、どんどん先へ進んでいきます。
大人はついていくのに必死です(笑)
🪵 最初からスリル満点!
コースの序盤には、いきなりロープで池を飛び越えるアスレチックが登場!
タイミングを間違えるとドボンッと水の中へ…。
朝からすでにずぶ濡れになっている子もいました。ほかのアスレチックが濡れているとできなくなってしまう、と注意書きもあり、それでも「できるからやりたい!」と主張する子どもと、「今はやめておこう」と止めたい大人とのせめぎあい…どこの家庭も同じ光景でした(笑)
⚠️ 人気の「ありじごく」
途中で見えてくるのが、大人気の「ありじごくランニング」。
これは名前の通り、すり鉢状の坂を全力で走って登るタイプのアスレチックです。
中に入ると傾斜がぐるりと円を描いていて、走っても走っても滑り落ちそうになるというスリル満点の遊具。
成功するには勢いとタイミングが大事で、見ているだけでも大盛り上がり!

ありじごくは定員10名で、まずは子ども、そのあとに大人が挑戦します。
うちの1年生も果敢に挑みましたが、途中で転んでしまい坂を転げ落ちてしまって号泣でした。
すぐにスタッフさんがロープで救助してくれて、外に出ることができたので安心でした。
外で泣いていたら見回りのおじさんが声をかけてくれて、「もし腫れがひどくなったら受付に行ってね」と優しく言ってくださり、その対応にもとても感謝しました。
最後に挑戦の大人はみんなが見守る中絶対に失敗できないプレッシャーがすごかったです(笑)
普段運動不足な大人は入念な準備運動をお勧めします!
ありじごくのあとも、コースはまだまだ続きます。
その後も20個以上の種目がありどれも体全体を使う本格的なものばかり。
ロープを握りしめて高さのあるところを渡るアスレチックでは、できないー!!動けないー!!と少し半べそをかきながらもどうにか一歩ずつ前へ。どうにもこうにも助けられる高さではないので自分自身でどうにかしなければならず、下から応援するばかりでしたが、怖さを乗り越えて進む姿に成長を感じました!
込み合っていたので1時間半ほどで40種目すべて終わらせると親はぐったりです。
🍱お昼ご飯
ここで早めのお昼にします。
園内にはお弁当を食べられるスペースがたくさんあり、
私たちは芝生の上にレジャーシートを広げてランチタイムにしました。外で食べるお弁当はおいしいですよね~!
屋根付きのテーブル席も人気で、皆さん早めに荷物で場所取りをしている様子。
もし座ってゆっくり食べたい方は、早めの時間に確保するのがおすすめです。
近くの売店はお昼時でかなり込み合っていて、軽食を買うにも列ができていました。

🧗♀️ 午後は「冒険コース」へ!
お腹を満たしたあとは、次のステージへ!
今度は「冒険コース」に挑戦しました。
午前中にチャレンジコースでかなり体力を使いましたが、子どもはまだまだ元気いっぱい。
このコースも全40種目。
中盤からは少しだけ水上にかかるエリアもあり、チャレンジコースとはまた違ったスリルがあります。
個人的にはチャレンジコースより難しく感じた場面もありました。
幼児も一部OK!元気いっぱいの子どもたち
冒険コースもチャレンジコースも、基本的には「幼児禁止」と書かれた種目以外は幼児も参加OK。
わが家の子どもたちは午前中にチャレンジコースを経験していたおかげか、慣れた様子でどんどん進んでいきました。
体力がすごい…!大人はもうクタクタです(笑)
🌊 34番からは水上エリアへ!
コースを進んでいくと、34番あたりから水上コースへと誘われる構成になっています。
入口にはスタッフの方が立っていて、
「途中まで行って戻ってこれますか?」と質問したところ、迂回コースもあるとのことでした。
平均台のような細い板を渡って進む形で、無理せず戻ることもできるそうです。
ただし、35・36・40番は陸上コースになっていて、水に入らなくても挑戦可能。
せっかくなので、少し進んでみることにしました。
👨👧 姉は全制覇!👩👦 弟も最後まで挑戦!
姉はパパと一緒に全コース制覇!迂回コースについて聞いてみたところ、それを使って戻る方が難しそうだったとのこと、迂回じゃないじゃん(笑)つかまるところなさそうだし、だそうです。
2人はなんとか無事に濡れずにゴール! 怖かったと言っていたけど本当にがんばりました。
一方、弟は私と一緒に36番まで進んで引き返し、最後の40番通ってゴールしました。
途中で難しい種目もあり、できなかったところもあったので少し不満そうでしたが、
それでも最後まで一生懸命に頑張りました。
途中であきらめずに挑戦する姿に、また一つ成長を感じました。
💡 これから行く人へ!清水公園アスレチックの持ち物&注意点まとめ
今回、実際に1日たっぷり遊んでみて感じた「これは持って行ってよかった」「次はこうしたい」というポイントをまとめました。
これから行く方の参考になればうれしいです!
🎒 持って行ってよかったもの
- 水筒(必須!)
とにかく体を動かすので水分補給はこまめに。売店もありますが混むので、自分の飲み物を持って行くのがおすすめ。 - 着替え・タオル
水上コースは濡れる可能性大。全身替えがあると安心です。 - 軍手・滑りにくい靴
ロープや丸太を握る場面が多く、軍手があると安全。サンダルは禁止なので注意! - レジャーシート
芝生でお弁当を食べるなら必需品。屋根付きテーブルは混むので、ピクニックスタイルが快適。 - 小銭
ロッカーは有料でお金が戻らないタイプなので、100円玉をいくつか持っておくと安心。
注意したいポイント
- 靴はサンダルNG!
アスレチック内はサンダルでは入れません。入口でレンタル靴がありますが、サイズや数に限りあり。 - ロッカー利用時はお金が戻らない
貴重品以外は預けて、できるだけ身軽に。 - 混雑対策
売店やテーブル席は昼前から混み始めるので、早めの昼食がおすすめ。 - 子どもが濡れたときの対応
更衣室があるので安心。濡れた服を入れるビニール袋があると便利。 - コース選びの目安
チャレンジコースは中〜上級向け、冒険コースは小学生以上におすすめ。
幼児は「幼児禁止」と書かれた以外の種目なら一部体験可能。別途幼児専用コースもあり。
まとめ
清水公園のフィールドアスレチックは、子どもが夢中になるだけでなく、大人も本気で楽しめる充実した施設でした!
自然の中で体を動かす心地よさと、子どもたちの成長を感じられる貴重な時間。
次は水上コースにも挑戦してみたいと思います!
清水公園は他にもBBQ施設やニジマス釣り、花ファンタジアなどもありまた訪れたい公園でした!
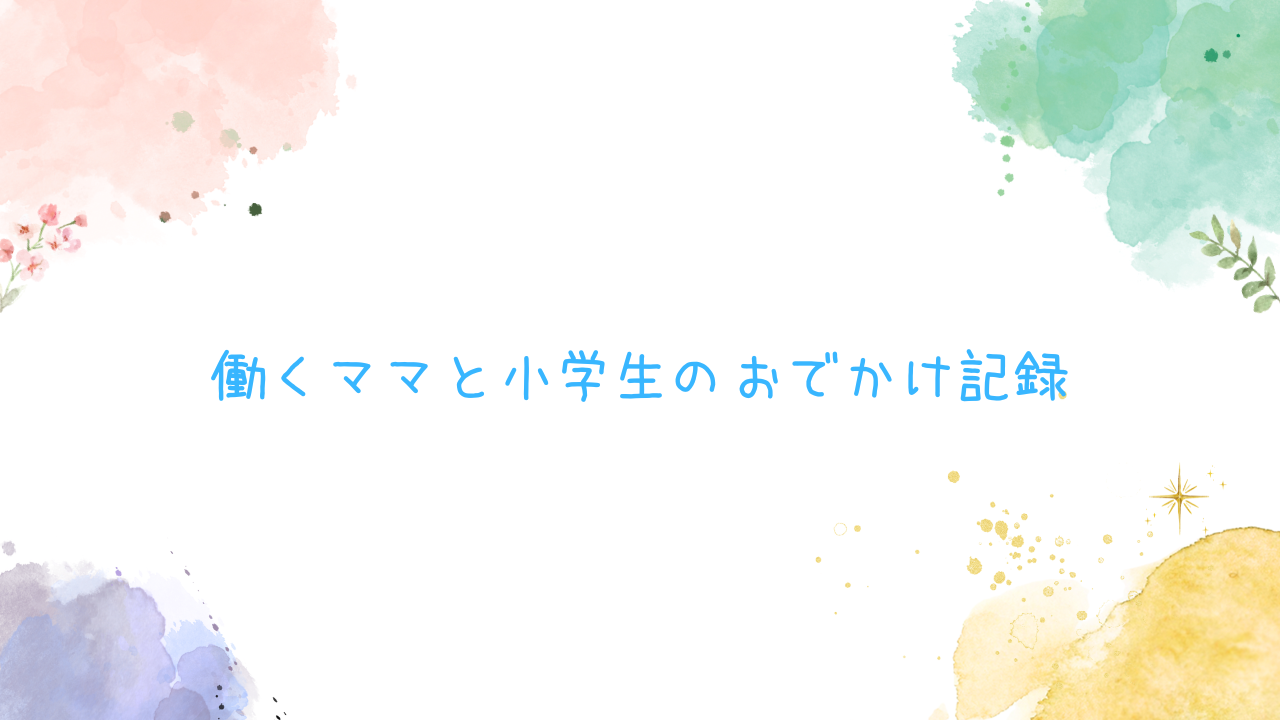
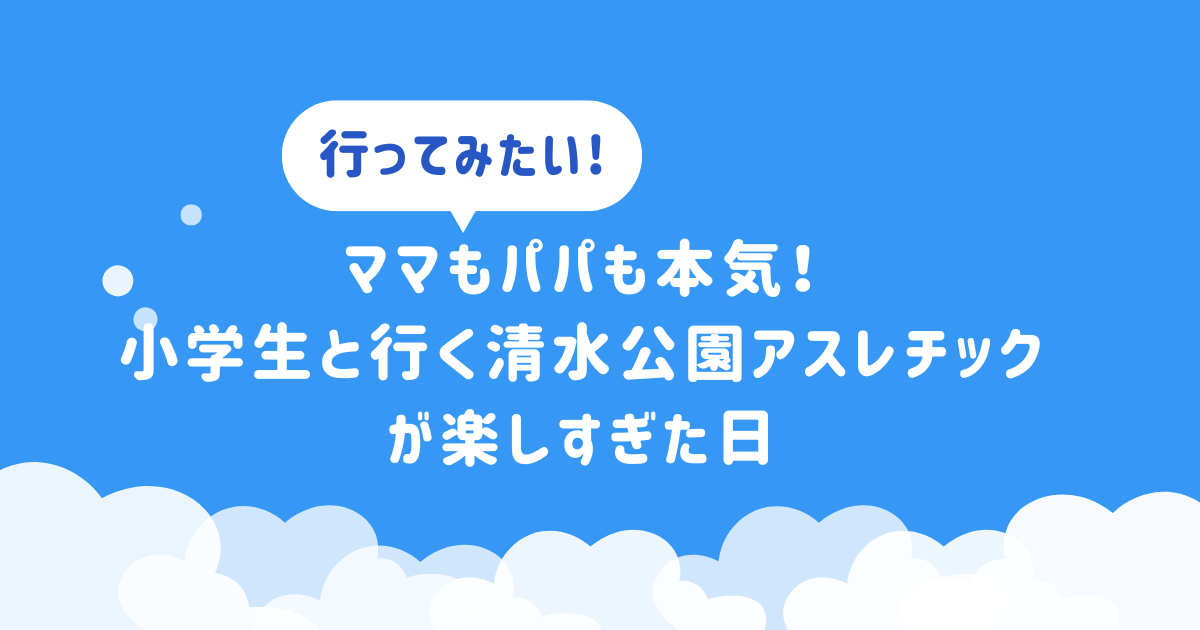


コメント